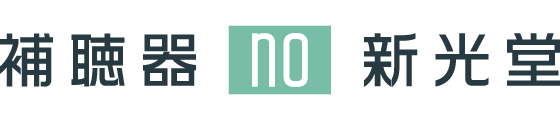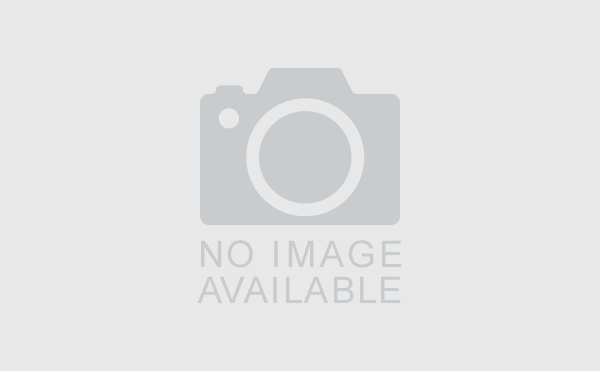70代からの”聞こえ”との向き合い方 ― 補聴器はまだ早い?と思った時に読むブログ
導入文:
本記事は、70代のS様からの「補聴器はまだ早いと思っているが、気にはなる」とのお問い合わせを受けて作成しました。「聞こえにくさの自覚はないが、家族に補聴器が必要だった」「認知症との関係が気になる」「聞こえづらくなったら耳鼻科へ行くべき?」など、多くの方が感じる不安や疑問に、認定補聴器技能者の立場からお答えします。

1. 聞こえにくさは突然ではなく、じわじわと始まる
難聴は、徐々に進行するケースが多く、ご本人が気づきにくいのが特徴です。特に感音性難聴(内耳や聴神経に関わる難聴)は、「言葉の聞き分け」が難しくなるのが最初の兆候で、「テレビは聞こえるけど、会話が聞き取りにくい」と感じるようになります。
このような変化は、本人よりもご家族のほうが先に気づくことも多く、「最近、返事が遅い」「テレビの音が大きい」といった指摘がヒントになります。
補聴器で改善される「語音明瞭度」は、単に音が聞こえるかではなく、脳が言葉を正しく理解できているかを表す大切な指標です【参考:語音明瞭度とは.pdf】。
2. 認知症との関係は?
近年、難聴と認知症の関連性が多くの研究で明らかになっています。音の情報が脳に届かない状態が続くと、脳の聴覚領域が刺激を失い、記憶や判断力などの認知機能に悪影響を与えることが知られています。
実際、難聴がある高齢者は、そうでない方に比べて認知症のリスクが約2倍以上というデータも報告されています(参考:聴こえ8030運動とは.pdf)。
また、補聴器を使用することで、社会的なつながりや会話が戻り、認知機能の維持に貢献するという研究結果もあります【参考:補聴器を活用するために(柘植勇人 医師)】。
3. 補聴器は “最後の手段” ではありません
「補聴器は必要になったらつければいい」と考えがちですが、実は聞こえと脳のリハビリ機器として、早めの装用が効果的です。
当店の「きこえリフレッシュプログラム」では、現在の聴力や語音明瞭度を評価したうえで、段階的に脳と耳を慣らすサポートを行っています【参考:きこえリフレッシュプログラム.docx】。
聞こえの不自由を自覚する前から補聴器を活用することで、より自然な聞こえを維持しやすくなります。
また、「補聴器をつけたら逆にうるさい」という声は、脳が久しぶりに音刺激を受けた反応であり、正しく調整と慣れの時間を設ければ、多くの方が自然な聞こえを取り戻しています【参考:補聴器を活用するために(柘植勇人 医師)】。
4. 耳鼻科にはいつ行けばいい?
耳鼻咽喉科の受診は、以下のような場合におすすめです:
- 家族や周囲から「聞こえていない」と指摘されたとき
- 雑音の中で会話が聞き取りにくいと感じるとき
- 電話やテレビの音声が不明瞭に感じるとき
まずは耳の病気(中耳炎や耳垢など)の有無を確認するためにも、
聴力の変化を感じたら専門医の診察を受けることが大切です。
補聴器相談医が在籍する医療機関を紹介することも可能ですので、お気軽に当店へご相談ください。
5. 「話だけでも聞いてみたい」方へ
S様のように、「まだ早いかもしれないけど、気になる」という段階でのご相談は、とても良いタイミングです。
補聴器の新光堂では、聴力測定や聞こえのご相談を随時実施しております。
無理に補聴器をすすめることはせず、「今のあなたに必要なことは何か?」を一緒に考えます。
また、すでに補聴器をお持ちの方でも、「音が合っていない」「うまく使えていない」と感じる場合は、他店購入品でも調整対応が可能です。
ぜひ、お気軽にお話だけでも聞きに来てください。
まとめ:
補聴器は「つけるか・つけないか」の話ではなく、「どう聞こえて、どう生活するか」を考える道具です。
聞こえにくさは、気づいた時が対処のチャンス。ぜひ、今の聞こえを知ることから始めてみませんか?
参考文献・出典一覧:
- 『語音明瞭度とは』補聴器の新光堂 配布資料(2024年版)
- 『聴こえ8030運動とは』日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 『補聴器を活用するために』柘植勇人 医師(日本赤十字愛知医療センター)
- 『きこえリフレッシュプログラム』補聴器の新光堂 独自プログラム説明書
桑名市 補聴器の新光堂 認定補聴器技能者 吉原育代